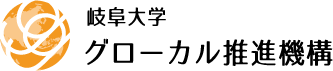令和7年3月3日(月)~3月5日(水)、本学はインド工科大学グワハティ校(IITG)とグワハティ ジョイント・ディグリーシンポジウム2025を共同開催いたしました。このシンポジウムは、本学とIITG(本学とのジョイント・ディグリープログラム(JDP)開設大学)が現在進めている「大学の世界展開力強化事業~インド太平洋地域等との大学間交流形成支援~」の活動の一環で実施されたものです。
今回のシンポジウムは、JDPを始めとする国際協働教育と社会変革に必要な研究開発について、インド農村開発ならびにインド北東部(NER)開発を加速する日印連携についての議論を目的に、IITGキャンパスにおいてハイブリッド形式で開催されました。本シンポジウムには、2日間でオンラインを含む延べ176名の方にご参加いただきました。
シンポジウム初日の開会式では、Rohit Sinha IITG教授より歓迎の挨拶に続き、Sumana Dutta IITG教授と小山 博之 グローカル推進機構長よる趣旨説明ののち、吉田 和弘 岐阜大学学長(ビデオメッセージ)およびK. V. Krishna 学長代理より開会の挨拶に続き、Sibi George 在日本インド大使からの祝辞がビデオメッセージとして上映されました。その後、渡辺 真人 在日本インド大使館 一等書記官とGautam Barua 教授より基調講演を賜りました。
また、開会式では、同時期に開催されるスプリングスクール(短期プログラム)の開会式が執り行われ、プログラムコーディネーターのChandan Das IITG教授からのプログラム紹介後に、プログラムに参加する10名の岐阜大学学生が紹介されました。
その後のアカデミア連携セッションでは、NER(北東部地域)の機関が紹介され、日本の大学関係者(東京大学、筑波大学)および日本の政府機関(JST(科学技術振興機構)、JSPS(日本学術振興会))からの活動紹介がされました。午後からのセッションでは、日印大学教員、日本の政府機関(JETRO(日本貿易振興機構)、JICA(国際協力機構))ならびにシンポジウム参加企業が紹介され、活動紹介をいただきました。また、大学連携では、日印の大学・研究機関ならびに日印の企業関係者との間で円卓会議を行い、今後の連携について深く議論することができ、議論の中で今後、IITGを含むインドの7大学による「北東インド大学コンソーシアム(仮称)」をIITGにて組織することなど意見交換がされました。その後、インドの学生および研究者など33名によるポスターセッションが行われ、岐阜大学の教員も審査員として参加いたしました。
シンポジウム2日目は、バイオ/生命科学セッションおよびスマート/インテリジェントセッションの2セッションに分かれて執り行われました。
バイオ/生命科学セッションでは、日印両大学教員が議長となり、10名の登壇者による基調講演および一般講演が行われました。基調講演では、藤田 盛久 岐阜大学教授より「Decoding the "Life of Glycan" with genetic and glycomaple strategies」について講演されました。また、スマート/インテリジェントセッションでも、日印両大学の教員が議長を務め、日印の大学関係者9名の登壇者による基調講演および一般講演が行われました。基調講演では、茂木 健一郎 岐阜大学客員教授が「AIのアライメントと人間の脳」をテーマにご講演されました。さらに、IITGキャリア開発センター(CCD, Centre for Career Development)の主催で、インド学生に対する人材採用を念頭に置いた日本企業のプレゼンならびに留学生受入が可能な本学の研究所・センターの紹介を行い、日本企業への就職や日本留学に関する情報が提供されました。
シンポジウム3日目に行われた研究施設・企業訪問では、IITG近隣にあるグワハティ大学への表敬訪問ならび研究施設見学、バイオ企業訪問、デジタル設計および3Dプリンターに関するCOEの見学を行い、NERとの大学連携ならびにNERにおける生物資源および研究技術開発の現場に対する理解を深めることができました。