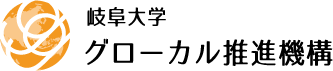基本情報
国際共同学位プログラムで両国地域の"食品及び関連産業の発展"を牽引する人材を育成(修士課程)
本専攻では、留学を伴う国際的な教育環境の中で、食品科学技術に関する専門性、デザイン思考活用力、英語を共通言語としてコミュニケーションする力、国際的対応力(異文化適応力と国際的協働力)ならびに産業を牽引するリーダーとしての資質を有する人材育成のための教育研究を行います。
主な学問領域:食品工学、微生物学、生物工学、生命科学、食品科学、栄養学、数理工学、化学工学など
アドミッションポリシー
本専攻では、以下のような資質が必要となります。
①化学及び生物学を中心とする専門的な学理と技術を既に修得し、さらに食品科学技術に関する高い専門性を得ようとするもの
②能動的な研究活動を実践する意欲のあるもの
③英語を共通言語とし留学を伴う教育環境で学ぶ意欲のあるもの
④文化的な違いに適応し協働する意欲と産業界のリーダーとなる意志をもつもの
国際連携専攻について
国際連携専攻(ジョイント・ディグリープログラム)とは、本学と海外協定大学がそれぞれの強みを活かしたカリキュラムをもとに、共同で作成する教育プログラムです。学生は本学と海外協定大学の両方に在籍して修学し、標準修業年限の中で一定期間を相手大学で学びます。留学を伴う国際的な教育環境の中で講義履修および研究活動を行い、在学期間を延長することなく日本と海外における2大学の連名で、単一の学位を取得することができます。
インド工科大学グワハティ校について
インド工科大学は、工学と科学技術を専門とした国立大学としてインド各地に20校余りが設立されています。グワハティ校は、その第6校目として1994年にアッサム州のグワハティ市に設立され、翌年開学し現在に至ります。B. Tech.、B. Des.、M. A.、M. Des.、M. Tech.、M. Sc.、Ph. D.プログラムを提供する11の学部と5つの学際領域センターがあり、工学、科学、人文科学の主要分野を網羅しているほか、高度な研究を行うための世界クラスの施設が整備されており、最先端の科学技術装置も備えています。
インド工科大学グワハティ校HPはこちら
研究科・専攻
修士
| 専攻 | 入学定員 | 領域 | 募集人数 |
|---|---|---|---|
| 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻 | 10名 | 食品科学技術領域 | 5名(岐阜大学) |
備考
出願資格として、岐阜大学大学院自然科学技術研究科推薦入試、一般入試、社会人特別入試及び外国人留学生特別入試のいずれかに合格することが必要です。
学び方
| 入学料 | 入学料は徴収しません。 |
| 授業料 | 一年目の前期については全員免除します。その後、学期ごとに成績判定を行い、成績優秀者について授業料を免除します(標準修業年限内)。 |
| 独自奨学金・学費減免制度 | あり |
問い合わせ先
岐阜大学応用生物科学部学務係
〒501-1193 岐阜市柳戸1-1
TEL:(058)293-2838 FAX:(058)293-2841
nogaku@gifu-u.ac.jp
ホームページはこちらから
カリキュラム概要
東海地域とインド・アッサム州の地域特性を活かした国際協働教育
高度な食品加工技術を持つ東海地域と生物資源が豊富なインド北東地域アッサムの強みを活かし、両地域の課題を発見・解決できれば、双方の地域産業を活性化することができます。本専攻は、農学(応用生物科学)分野の岐阜大学と、工学分野のインド工科大学グワハティ校との間で、食品関連産業のイノベーションの基礎となる学問領域「食品科学技術」に関するカリキュラムを設けています。
カリキュラムポリシー
①連携を組む両大学の強みを活かした相乗的な教育を行う
②デザイン思考を取り入れた研究リテラシーの導入と修士論文研究の共同指導を行う
③日印双方向留学への配慮を行う(日印の学生が両国で共に学ぶ環境を作る)
④異文化や日印双方の産業界の理解を深め、国際的対応力を養う
ジョイント・ディグリープログラム(修士課程)のスケジュール及び履修モデルはこちら(PDF)
カリキュラム編成
授業科目
| 科目区分 | 授業科目名 | 開設大学 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 選択 必修 |
|||
| 研究科共通科目 | 科学コミュニケーション Scientific Communications |
GU | 1 | ||
| デザイン思考 Design Thinking |
GU | 2 | |||
| アカデミックキャリア Academic Career |
GU | 1 | |||
| 国際連携グローバルインターンシップ及びセミナー B International Joint Global Internship & Seminar-B |
共同 | 3 | |||
| 専門研究科目 | 修士論文研究第Ⅰ部 GU students Dissertation Part I |
GU | 1 | ||
| 修士論文研究第Ⅱ部a GU students Dissertation Part Ⅱa |
IITG | 4 | |||
| 修士論文研究第Ⅱ部b GU students Dissertation PartⅡb |
GU | 3 | |||
| 修士論文研究第Ⅲ部 GU students Dissertation Part III |
共同 | 8 | |||
| 修士論文研究第Ⅳ部 GU students Dissertation Part IV |
GU | 8 | |||
| 国際連携食品科学技術演習A International Joint Exercises in Food Science and Technology-A |
共同 | 1 | |||
| 国際連携食品科学技術演習B International Joint Exercises in Food Science and Technology-B |
共同 | 1 | |||
| 領域コア科目 | 食品化学特論 Advanced Topics in Food Biochemistry |
GU | 1 | ||
| 食品栄養学特論 Advanced Topics in Food and Nutritional Biochemistry |
GU | 1 | |||
| 食品微生物学特論 Advanced Topics in Food Microbiology |
GU | 1 | |||
| 先端食品加工学 Advanced Food Processing |
IITG | 3 | |||
| 専門科目 | 食品科学特論 Advanced Topics in Food Science |
GU | 1 | ||
| Advanced Topics in Food Chemistry | GU | 1 | |||
| Advanced Topics in Food Engineering | GU | 1 | |||
| 食品保蔵加工学特論 Advanced Topics in Food Preserving and Processing Technology |
GU | 1 | |||
| Advanced Topics in Molecular Life Science: Biological Aspects | GU | 1 | |||
| 植物トランスレーショナル研究特論 Advanced Topics of Plant Translational Research |
GU | 1 | |||
| 天然物化学特論 Advanced Topics in Natural Products Chemistry |
GU | 1 | |||
| 数理的手法序論 Introduction to Numerical Methods and Statistics for Food Scientists and Engineers |
GU | 2 | |||
| 最適化論 Optimization Techniques |
IITG | 3 | |||
| 膜工学 Membranes |
IITG | 3 | |||
| 多成分物質移動論 Multicomponent Mass Transfer |
IITG | 3 | |||
| 生体分子プロセス工学及び細胞プロセス工学 Biomolecular and Cellular process engineering |
IITG | 3 | |||
| 微生物生物工学 Microbial Biotechnology |
IITG | 3 | |||
| 生物プロセス工学 Bioprocess engineering |
IITG | 3 | |||
| 植物バイオテクノロジー Plant Biotechnology |
IITG | 3 | |||
| バイオセンサー Biosensors |
IITG | 3 | |||
| 工業廃液汚染制御学 Industrial Wastewater Pollution Control |
IITG | 3 | |||
| 生存管理及び農学的技術 Livelihood Management and Agro Technology |
IITG | 3 | |||
| 食品産業及び生物プロセス産業における生産物開発及びプロセス開発 Product and Process Development in Food & Bioprocessing industries |
IITG | 3 | |||
※すべての講義は英語で行われます。
修了要件
JDプログラムに2年以上(最大4年)在籍し、主大学開講科目より15単位以上、副大学開講科目より10単位以上、共同開設科目より5単位、合計48単位以上を修得する必要があります。
教員紹介
専攻長 西津 貴久 教授 (岐阜大学):食品工学

13億を超える人口を抱えて高い経済成長を続ける若いインドも、超少子高齢化を迎えた日本も、それぞれ食品ロスと食品廃棄が課題となっています。私の専門に関係の深い「食品加工」はそもそも、次の獲物が取れるまで、また次の収穫時期まで貯蔵するために祖先が生み出してきた技術であり、変質による廃棄の量を減らすことに大いに役立ってきました。言い換えれば、食品加工は国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」に対する古典的な解のひとつであると言えます。現在グローバルな課題となっている食品ロス・廃棄の解決に向けて、日印両大学で最新の食品科学技術を習得し、SDGsに対する最新の解を一緒に見つけてみませんか?
海老原 章郎 教授 (岐阜大学):酵素科学

私は本専攻におけるインド工科大学グワハティ校との調整担当教員です。皆さんが本専攻に入学した際には様々な面でサポートをする立場にあります。ご存じのようにインドの経済成長は著しく、国連の予測では2024年には人口世界1位となることが発表されています。インドに度々渡航する中で、農産物が加工されないまま路上で売られている現状を見てきました。本専攻で学んだ日印の修了生が協働して、農産物の高付加価値化事業に携わることも夢ではありません。
私自身は、生活習慣の変化に伴いインド・バングラデシュで増加の一途を辿る糖尿病患者数に着目し、今後増加が予想される糖尿病合併症の早期診断分子マーカーの検査法開発を目標に、日印番3か国で国際共同研究を進めています。食品加工に限らず、変貌を遂げつつあるインドで様々な興味を持って挑戦してみたい学生諸君を待っています。
柳瀬 笑子 准教授 (岐阜大学):生物有機化学

私は、様々な植物から特にヒトの健康に役立つような機能性成分の探索、さらに、それらが食品加工の過程で受ける変化について有機化学的な視点から明らかにすることを目指して研究を行っています。インド工科大学グワハティ校のある北東インドは生物資源の宝庫であり、天然物化学者にとって大変魅力的な地域です。この地域特有の植物資源について、この専攻の教員や日印の学生さんとともに共同研究をすることで、新たな機能性成分を発見し、将来的にその成果がこの地域の農産物の価値を高めて地域産業に貢献できたらいいですね。
チャタルベジ ラキ 教授 (インド工科大学グワハティ校):植物分子細胞育種学

アーユルヴェーダで薬木として利用されてきたニーム(Azadirachta indica:インドセンダン)やお茶(Camellia sinensis:チャノキ)等、薬用および商業的価値のある様々な植物を研究材料としています。このような植物を、育成環境に左右されずに利用できるよう、品種改良や細胞体での培養方法(マイクロプロパゲーション等)の研究を行っています。
カティアール ヴィマル 教授 (インド工科大学グワハティ校):バイオポリマー

従来の非分解性プラスチックは地球に大きな環境負荷を与えています。従来型プラスチック社会からの脱却に向け、我々は、石油からではなく生物由来(廃棄バイオマス)の原材料を用いて、生分解性プラスチックを低コストで合成する方法を確立しようとしています。我々の生分解性プラスチックは熱湯をかけても変形せず、自然界にて分解された後は土壌に吸収され、環境負荷を抑えることができます。持続可能な社会の構築に向けて、このプラスチックを様々な分野(食品皿や食品を覆うフィルム)に利用されるよう、日夜研究を行っています。
その他、本専攻には両大学から多くの教員が参画しています。
詳細はこちら(PDF)