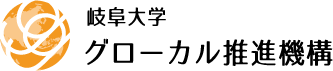ジョイント・ディグリーを語る-大学教育の新しい制度を導入した経緯・魅力とは-


野々村 北岡課長は文部科学省の大学振興課時代に、ジョイント・ディグリー(JD)のガイドライン作成に携わられたと伺っております。私たちは皆このガイドラインに従って、JDの立ち上げをしているところですが、JD制度を日本に導入しようとされた当時の背景を教えていただけないでしょうか。
北 岡 日本の大学の課題についてよく言われることに、"国際的な展開が非常に弱い"ということがあります。学生が外に出たがらないということが一つですが、もう一つは大学の教員側も、海外とのつながり、あるいは海外への進出というものをあまり意識しない傾向があるということが常々言われてきました。
そこで、世界的に活躍できる人材を育成することも大学の役割であるという考えのもとで、日本の大学が海外の先進的な教育研究機関と連携して教育・研究を行う土壌を整え、海外の学問、学びというものを経験した学生をしっかりと日本国内でも育成できるような仕組みを作る必要があるということで考えられたのが、海外の大学との連携による共同学位制度です。
もちろん、ダブル・ディグリーというような、単位互換制度に近い形での共同学位はあるものの、ダブル・ディグリーの場合は、単位互換の枠内でやることが前提にありましたので、(国内大学と海外大学の)二つの教育課程をすべて取り終えなければならないという点から、修業年限が長くなってしまったり、あるいは、海外大学との間で発生する授業料等、非常に経費がかかるというのが問題になっていました。
このような背景のもと、複数大学で一つのプログラムを構築することにより、学生にとっても、大学にとっても、より効率的かつ効果的な共同学位制度というものが作れないか、そういう思いで考えられたものがJDプログラムになります。
野々村 JDを作成される過程で、ハードルが高かったことや、ここが困った、といったことなどはありましたでしょうか。
北 岡 ご存じかとは思いますが、JDは日本ではもともと出来ない制度でした。まず、日本の場合、「大学設置基準」の中で、"自ら開設"という基本ルールがありますので、大学は「単位を与えて、卒業させて、学位を与える」という、教育プログラムはすべて自前で作らなければならない、という決まりがありました。大学が大学たる根幹とも言える「学位を与える」というところに、他所の力というものを借りてよいのか、更に言うと、海外の大学というのは、日本の国内法令の中では学校でもなんでもない組織になりますので、そのような組織・機関というものを(教育に)取り込んでよいのか、というものもありました。
ただ、JDがそこを乗り越えられた理由として、国際的にアクレディテーションの仕組み(日本で言う認証評価に類する仕組み)がしっかりしているので、この仕組みが導入されている高等教育機関については、教育の質の保証という点はクリアできるのではないかということで、ハードルを乗り越えていったということがあります。
野々村 今回、岐阜大学は四つの国際連携専攻を同時に立ち上げる予定です。しかもそれが農学系と工学系であり、そのうち一つは修士も含まれます。それをお聞きになった際は、どのような感想をお持ちになりましたか。
北 岡 大変大胆だなと思いました(笑)。まず修士でやるということは、かなりハードルが高いのではないかという思いがありましたので、そこにチャレンジいただけるのはすごく有難いと思いました。アカデミアの世界に入ることを想定しておられる博士の方々は、このJDという仕組みというものに魅力を感じると思います。一方、修士、特に理科系修士の場合は、修了後の出口が多くの場合は民間企業であり、必ずしもアカデミアではないという考えがあるので、学位というものがどれだけ"価値"を持つのかというところが若干疑問でした。そこに敢えてチャレンジするというのは、なかなか大した度胸だなと言う印象をもったというのが、当時の記憶です。

野々村 岐阜大学なりの地域貢献ですとか、人材育成などを、特徴を持たせてやっていくということもJDの取り組みに入ってくると考えています。
北岡課長から見て、JD専攻で育つ人材像はどのようなものをお持ちでしょうか。
北 岡 まず一つは、やはりJDの学生というのは、自ら海外の学修を経験したいという思いから飛び込んでいく積極的な学生ですので、その人達は、日本にとどまらず世界で活躍できるようになって欲しいという思いがあります。そのためには、JDで育った学生さんたちがきちんと企業なり社会から認知されて、評価されなければならないということがあります。そういう意味ではJDに取り組んでいただける各大学にはそれらの学生の優位性、立派なところ、というものをしっかりとアピールしていだたいて、このJD専攻を終えた学生たちが世界に活躍できるような下支えをしていただきたいという思いを持っています。
野々村 そういう意味では岐阜大学内での人材養成だけでなく、その先、実際に社会で活躍できるようになっているかというあたりが、次の課題ということになりますね。
北 岡 そうですね。専門性というものは大学院を出ておられれば、ある一定程度身につけておられるということ、これはもう修士という学位で証明されていると思うのですが、その過程で、わざわざ外国の大学で学問を学ぶという意欲を持った人たちを、しっかり評価してあげるというような仕組みが必要だと思います。また、今の企業は国際化にはかなり力を入れて取り組まれていますけれど、どちらかと言うとターゲットとなる地域の外国人学生をそのまま採るという発想になりがちだと感じています。日本国内でも、外国人留学生だけでなく、海外大学の経験を積んだ学生たちがいるということを、しっかりと企業の方に見ていただけたらと思います。
野々村 岐阜大学のJDの相手はインド、それからマレーシアという国になります。最初、JDを導入されたときに、どのあたりの国、例えば欧米系の国のイメージをされていたのか、それともアジア諸国であったのか等相手国のイメージはお持ちでしたか。

北 岡 おそらくJDの議論をした時に、多くの人は欧米の大学を想定していたみたいですけれども、当時の高等教育で担当した者の間では、やはり日本の大学を必要と感じる所というのは、欧米というより東南アジアあるいは南米といった地域ではないかという想定はありました。また、特に日本としっかり連携しようとしてくださる所は、その国においてはトップクラスの大学ですので、そういう大学と組んで、研究力の高さを知っていただくのは、日本の大学にとっても非常に意味があることだと思います。
野々村 まさに今、北岡課長がおっしゃったように、本学の相手大学であるインド工科大学グワハティ校もインド国内において非常にレベルの高い大学であり、マレーシア国民大学も国を代表する大学ですので、そういう意味ではその国の非常にレベルの高い大学と岐阜大学という国立大学が一緒にやるというのは大学の国際化という面で意味があるのかなと思っております。
北 岡 その通りだと思います。大学というのはどのような大学であっても世界のトップレベルと戦っていかなければ、その研究というものは前に進んでいきませんので、そういう世界の最先端と手を取り合って、高みを目指していける関係というものは、非常に重要だと思っております。
野々村 大変心強いお話を聞かせて頂きました。本日はお時間を頂きありがとうございました。